コツを掴めば意外と簡単、ぜひ味わいたいレシピです。
硬い鬼皮をむくのにひと工夫です。
材量
| 栗 | 500g |
| 砂糖 | 150g~200g |
| 重曹 | 大さじ2 |
栗の渋皮煮 レシピ・作り方

- 1栗をむきます。
- 熱湯に栗を入れ10分置きます。
- 温めることで鬼皮(外側の硬い皮)が柔らかくむきやすくなります。
- ざらざらした底の部分をそぐようにして削り取ります。
- つるっとした先端の部分は簡単に抜けます。
- 10個ほどむくと、お湯が冷えてきます。その時はもう一度温めます。
黄色い部分が出てきてもそのまま作業を勧めます。煮崩れてもそれなりに出来上がります。

- 2栗を煮ます。
- たっぷりのお湯に大さじ1の重曹を入れ10分ほど中火にかけ一晩おきます。
- 水を取り替え、重曹大さじ2ぶんの1を入れ10分中火で煮ます。
- 手が付けられるほどの温度になったら筋をとったり表面を指先でこするようにしてきれいにします。
- 水を取りかえ再び重曹大さじ2分の1を入れ、中火で10分煮ます。
- 水を取り替え、中火で5分ほど煮ます。
- もう一度水を取り替え中火で5分ほど煮ます。
- 水を取り替えひたひたの水を入れ、砂糖を加えて中火から弱火で10分ほど煮こみます。
- 好みでブランデー(小さじ1~2)、しょうゆ(小さじ1)を加えます。
料理のポイント・コツ
鬼皮をむいてからはぐらぐら沸騰させないようにします。
砂糖を入れてからは焦げないように注意します。
鬼皮をむく時に黄色い部分が出ないようにします。
多少煮崩れても良いですががひどいときは途中で取り出してください。
重曹を抜くために水で2回煮ます。
多少ゆで汁に色は残りますが重曹で煮ている時とは違います。
重曹で煮た後水を流しておく方法もありますが、2~3度取り換える程度でかまいません。
色々な意見があるとは思いますが、1個も煮崩れないように丁寧にやるより気軽に作ったほうが良いと思います。少しぐらい煮崩れたものが出てもかまわないと気楽に作ってください。
栗は意外に日持ちしません。購入したら1~2日の内に調理してください。
おつまみに最適♪栗の素揚げ レシピ・作り方

- 作り方2の1の段階、一晩重曹につけてあくを抜いた栗の表面をきれいに洗います。
- 水気をふき取り160度の食用油で10分揚げます。
- 油をきって塩を振って出来上がりです。
1人前2~3個が適当だと思います。
もう少食べたいと思う程度が適量です。
コーヒーブレイク
栗の素揚げは今年初めて知りました。
渋皮煮を作るついでに作ったわりには美味しいです。冷やした日本酒に合うように思います。茹でて半分に切ってスプーンで食べるのもいいですが、素揚げの栗2,3個で冷酒を頂く。他にキュウリとかアスパラで作った小鉢を一つ。豊かな気持ちになれそうです。
渋皮煮は辰巳浜子先生の本で知りました。中学生の頃です。重曹ではなくわらを焼いた灰の上澄み液で渋抜きします。わらが手に入らなくてわらに包んだ納豆をわざわざ探して使ったものでした。重曹でも十分うまくできます。
重曹の量はやや多めです。煮だす時間はやや短めです。水で2回煮ていますので重曹の渋みは抜けています。
ほんのり栗の渋みが感じられるのも風味だと思います。
渋皮煮は丁寧に作るものではなくざっくりとまた作ろうと思う程度の手間のかけ方でよいと思います。崩れないように注意してもしなくても2~3個分しか変わりませんし、煮崩れたものはよりダイレクトに甘みが入って違う風味が楽しめます。
若い頃は失敗しないように気負って新しい料理にチャレンジしたものです。それではとても疲れて2度と作りたくなくなります。完璧でなくてもそこそこ美味しければいいという気持ちでつくってもいいのでは?ただし、ポイントを押さえて基本は忘れずに料理します。
灰汁を使う料理として鹿児島のあく巻きという料理があります。農家の方に極上のわらび餅のようなあくまきを頂いたことがあります。
鹿児島の名産あくまきにも挑戦しましたが、こちらは農家のようにうまく行きません。
先ず、包む竹の皮の採取、灰汁を作る時の木の品種、とてもこだわって作られています。
美味しいと言われて嫌な気持ちになる人はいません。快くコツは教えてもらったけど実現不可能でした。昔の人は良く灰汁を料理に使うなんて思いついたものです。
韓国ドラマ「チャングム」ではかまどの土を使うシーンもありました。まだまだ知らない料理、そして消えていく食材や調理法もあるかもしれません。
料理って本当に終わりのないテーマです。
2021・9・20追記です。
生肉取り扱いのツイートを見て以来気になっていた自称フードライターさんのつぶやきです。
「栗は日なたに置いとくと甘くなる」
ええ?私も硬い皮のせいで日持ちがすると信じ切っていました。けれど、どうやら購入してすぐ調理したほうがよいと感じていたこの頃でした。で、ググってみました。
まずは乾燥させるのは良くない、密閉して冷蔵保存が良いそうです。栗は生きています。冬と勘違いして春に芽を出す準備を始め、甘みが増すそうです。また、水につけて浮くものは虫が入っている可能性があるそうです。八百屋さん、魚屋さんでお買い物してた頃はどうすればおいしくいただけますかと聞いて教えていただいたものです。今は生産者さんがホームページなどで教えてくれます。
自称フードライターさんに直接助言する勇気はなくて。以前には輪ゴムで束ねたソーメンを茹でるツイートと記事も。粗探ししてるようでこの方のツイートは見るのを止めようと思っていた矢先です。
食事を作るのは家族の健康を預かっているという事です。「人のフリ見てわがフリ直せ」ということわざもあります。私も慎重に発信しなければと改めて思いました。
栗の簡単なむき方2021・10・27の追記です。
1晩冷凍にしてたっぷりの熱湯につけて5分おきます。1個ずつ取り出して温かいうちにむきます。渋皮も簡単にむけます。本日動画で見たので、機会があれば検証したいと思います。この方法だと渋皮も簡単にむけるので渋皮までむいてからマロングラッセを作るのも良いかと思います。
2022・2・14追記です。
バレンタインデーのニュースです。フランスだったと思うのですが有名店のチョコの紹介がありました。日本語の上手なパリジェンヌが紹介したのはチョコではなくマロングラッセです。マロングラッセは渋皮まで剥いた洋酒の香り高い砂糖漬けにした栗です。日本では1個900円と消費税。パリジェンヌ曰く、ねっとりしてようかんのような食感だと。大きくて立派な栗ですが、1個900円!!ふつうのマロングラッセはいただいたことがあります。渋皮煮も負けていません。むしろ栗の風味は勝っているかも。気が早いですけれど、今年の秋はマロングラッセを作る気持ちの余裕があるかしらと考えています。
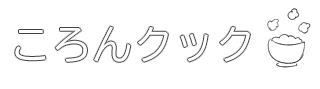


コメント